【現代語訳】2
「世の中の無常な有様を見ていると、生い先も短く何となく頼りなくて、勤行に励むことが多くなっておりますので、このようなご出産の後は騒がしい気がして参ることができませんが、いかがですか、ご気分はさわやかになりましたか。おいたわしいことです」と言って、御几帳の端からお覗き込みになった。御頭をお上げになって、
「やはり生きられそうにない気が致しますので、こうした私は罪障も重いことで、尼になって、ひょっとしてそのために生き残れるのではないかと試してみて、また死んだとしても、罪障をなくすことができるかと存じます」と、いつものご様子よりはとても大人らしく申し上げなさるので、
「まことに嫌な、縁起でもないお言葉です。どうしてそんなにまでお考えになるのですか。このようなことは、実際恐ろしい事でしょうが、それだからと言って命が永らえないというなら別ですが」と申し上げなさる。ご心中では、
「本当にそのようにお考えになっておっしゃるのならば、出家をさせてお世話申し上げるのも、思いやりのあることだろう。このように連れ添っていても、何かにつけて疎ましくお思いすることになるのがおいたわしいし、自分自身でも気持ちも改められそうになく、辛い仕打ちが折々まじるだろうから、自然と冷淡な態度だと人が見咎めることもあろうことが、まことに困ったことで、院などがお耳になさることも、すべて自分の至らなさからのこととなるであろう。ご病気にかこつけて、そのようにして差し上げようか」などとお考えになるが、また一方では、大変惜しくていたわしく、これほど若く生い先長いお髪を尼姿に削ぎ捨てるのはお気の毒なので、
「やはり強くお考えになるようにして下さい。心配なさることはありますまい。最期かと思われた人も平癒した例が身近にあるので、やはり頼みになる世の中です」などと申し上げなさって、御薬湯を差し上げなさる。とてもひどく青く痩せて、何とも言いようもなく頼りなげな状態で臥せっていらっしゃるご様子は、おっとりしていじらしいので、
「大層な過失があったにしても、心弱く許してしまいそうなご様子だな」と拝見なさる。
《夜の訪れは絶えて、昼、顔を出しての対話です。
源氏は、もっともらしい挨拶をしますが、無理もないと思うものの、いかにも白々しい感じです。「御几帳の端からお覗き込みになった」は「つめたい」と『評釈』も言います。
宮は、出家したいと訴えますが、「いつものご様子よりはとても大人らしく申し上げなさる」というところに、彼女のひとつ吹っ切れた、決意が感じられます。
「こうした私は罪障も重い」というのは、「お産で死ぬのは罪が重いと考えられていた」と『集成』は言うのですが、『評釈』は「ほかにこのような話は出てない」と言います。どういうことなのでしょうか。
出家の話は、源氏は、言下に否定しますが、内心では、宮の気持も理解できるので、それも一つの道だろうと考えています。
何と言っても、自分がもはや宮への愛情を取り返すことが出できそうになく、このままに不愉快な生活をするのは自分も煩わしいし、宮にも気の毒だ、そしてそういう不仲は自然と人が気づくことになろうが、そうなれば外聞も悪い、そしてそれは院のお耳に入らずにはいないだろうが、事情をご存じない院は、すべては私の「至らなさ」のせいだと考えられるだろう、いっそ出家をさせてあげた方が、宮にも私にも、いいのかもしれない、…。
と、ここまで考えて、改めて宮を見ると、しかしこの若い姫を尼にしてしまうのは何とも気の毒で、しかも「頼りなげな状態で臥せっていらっしゃるご様子は、おっとりしていじらしい」と、またぞろ好色の気持ちまで湧いてくる始末で、心が定まりません。
ところで、「何かにつけて疎ましくお思いすることになる」の原文は「ことに触れて心置かれたまはむ」と、ちょっと分かりにくい言い回しですが、「『れ』は受身」(『集成』)で、女三の宮が源氏によって心置かれ」なさるのでしょう。『評釈』が「女三が気兼ねするのが気の毒で、とは、いい気なもの」と言っているのは、恐らく、らしくない誤りで、こういうところを見つけると、嬉しくなります。
『評釈』は、このあたり、「いつもと違う女三の宮に、(源氏は)気力で負けている感じである」と女三の宮の切実な思いを重んじていますが、私にはやはり源氏の自己把握の厳しさ、さまざまな現実的な気配りといった、深謀遠慮の方に大人の物語といった読み応えを感じます。》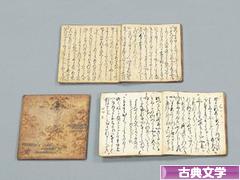
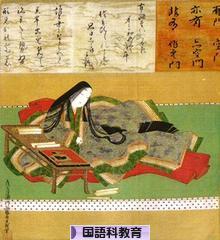

![]()
